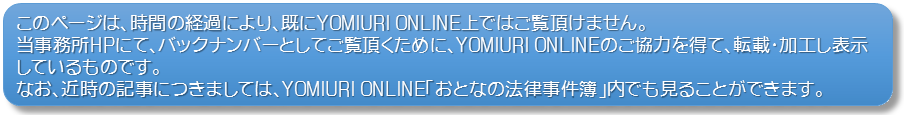婚外子差別は「違憲」 最高裁判決で相続はどうなる?
相談者 K.Cさん
私は、結婚していない男女の間に生まれた、いわゆる婚外子です。母が父と恋に落ちた時、父には妻子がいました。子供の頃は、それを理由に随分といじめにあい、一時は、両親を恨んだこともありました。でも、父も母も、私に深い愛情を注いでくれて、経済的にも恵まれた生活を送らせてもらい、今は、私を産み育ててくれた両親に感謝しています。
私自身も、今は夫と子供2人に恵まれて幸せな生活を送っていますが、結婚前は、奥さんのいる上司に恋心を抱いたこともあり、私を産んだ母の気持ちも理解できるようになりました。最近では、スケートの安藤美姫さんのように、結婚していなくても、出産したことを公表するようなケースが話題になるなど、婚外子を取り巻く環境も大きく変わったと思います。
ただ、昨年、父が亡くなったときに、すっかり忘れていた婚外子という自分の立場を思い知らされました。父の法律上の奥さんの代理人の弁護士さんから連絡があり、相続について説明を受ける機会があったのですが、その奥さんの子供は正式に結婚した夫婦の間で生まれたので、私の相続分の2倍の財産を受け取ることが出来るというのです。私としては、父の財産に固執するつもりは全くありませんが、自分が、結婚した夫婦の子供の2分の1の価値しかないのかと思い知らされた気がして、落ち込んでしまいました。
私は納得がいかなかったので、弁護士さんから提示された相続分割の合意書にサインせずに放置していたところ、先日、最高裁判所で、婚外子の相続について、法律婚の子供の2分の1とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反しているとして無効とするとの判決が出たことが新聞に大きく出ていました。判決が出たことで実際の相続にはどう影響するのでしょうか。判決の内容と併せて教えてくれますか。(最近の事例をもとに作成したフィクションです)
回答
最高裁判決は裁判官全員一致の結論
9月4日、最高裁判所は、「非嫡出子」(いわゆる「婚外子」、結婚していない男女間の子供のことを意味します。以下、判例の原文以外では、一般的に使われている「婚外子」の用語で統一します)の遺産相続分について、「嫡出子」(結婚した夫婦の子供)の半分とした民法900条4号ただし書きにつき、「法の下の平等」を保障した憲法14条1項に違反して違憲・無効とする、初の判断を示しました。
| 民法900条 |
|---|
|
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 |
この判断に従えば、たとえば、父親が1200万円の財産を残して亡くなり、相続人が母親と子供2名で子供の一方が婚外子と仮定した場合、母親は遺産の2分の1の600万円でその取り分は変わりませんが、子供2名は、従来の基準では600万円を2:1で分け400万円と200万円(婚外子)であったのが、平等に300万円ずつ受け取ることになります。
今回の最高裁判所の判決は、審理に参加した14人の裁判官全員一致の結論であり、菅官房長官もこの判決を受けて、「立法的手当ては当然。できる限り早く対応すべき」とコメントするなど、当然の結論という受け止め方が一般的と思われます。ただ、人間の本音が顕著に表れることの多いネット上で、まとめサイトなどを通じて世間の反応を探ってみると、必ずしも結論に
婚外子の差別に関する歴史的背景
本件問題は、過去における様々な背景を知っておくと、理解しやすい一面がありますので、その点につき簡単にご説明しておきたいと思います。
民法900条4号ただし書きの規定は、1898年(明治31年)施行の旧民法1004条ただし書きを引き継いだ規定となっています。当該規定の立法理由としては、法律婚の重視と我が国古来の慣行が挙げられていました。
戦後に行われた家族法改正作業の過程においては、婚外子の差別を廃止すべきとの意見もありましたが、正当な婚姻を尊重するため婚外子の相続分を嫡出子の半分とすることは「法の下の平等」に反しないとされ、民法900条4号ただし書きとして、婚外子の相続分を嫡出子の相続分の半分とする規定が存続することになったのです。
しかし、諸外国において、婚外子の地位を嫡出子の地位と同等に扱うという傾向が徐々に強まってきたことから、日本でも、相続法の改正作業の一環として、婚外子の相続分の見直しが検討されるようになり、1979年7月17日付で法務省民事局参事官室から公表された「相続に関する民法改正要綱試案」では、「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分と同等とするものとする」との提言がなされましたが、当時は、改正は時期尚早であるとして見送られています。その理由としては、(1)正当婚姻を尊重する国民感情が婚外子を嫡出子と同等に処遇することを許容するに至っていないこと(2)我が国における婚外子の出生率は0.8%と低率であること、などが挙げられています。特に、総理府が1979年に実施した世論調査において、民法の当該規定について、現行でよいとするものが47.8%と約半数を占め、婚外子の相続分を嫡出子と同等とすべきとするものは15.6%にとどまるという結果がでて、上記(1)に掲げた国民感情の問題が、改正見送りの大きな理由となったとされています。
最高裁判所判決の推移
民法900条4号ただし書きについて、最高裁判所は、1995年7月7日、合憲の判断を下しました。同決定の要旨は、「本件規定の立法理由は、嫡出子の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも配慮して、非嫡出子に嫡出子の2分の1の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護を図ったものと解され、現行民法が法律婚主義を採用している以上、右のような本件規定の立法理由にも合理的な根拠があり、本件規定が非嫡出子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の2分の1としたことが、右立法理由との関係において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって、本件規定は、合理的理由のない差別とはいえず、憲法14条1項に反するものとはいえない」というものでした。
しかし、この最高裁の決定は、15名の裁判官のうち、10名の裁判官の多数意見による判断であり、5名の裁判官からは反対意見が付されています。
反対意見の要旨は、「出生について非嫡出子自身何の責任もなく、その身分は自らの意思や努力によって変えることはできない。出生について何の責任も負わない非嫡出子をそのことを理由に法律上差別することは、婚姻の尊重・保護という立法目的の枠を超えるものであり、立法目的と手段との実質的関連性は認められず合理的であるということはできない。本件規定の立法理由は非嫡出子保護をも図ったものであるというのは、本件規定が社会に及ぼしている現実の影響に合致しない。1960年代以降、嫡出子と非嫡出子を同一に取り扱うように法を改正することが諸外国の立法の大勢となっているところ、市民的及び政治的権利に関する国際規約や児童の権利に関する条約等がかかる差別を禁止していること等を勘案すると、少なくとも今日の時点において、婚姻の尊重・保護という目的のために、相続において非嫡出子を差別することは、個人の尊重及び平等の原則に反し、立法目的と手段との間に実質的関連性を失っている」としています。
さらに、多数意見も、「ある法規の合理性が著しく失われて、憲法14条1項に照らし、到底容認できない段階に達しているときは、もはや立法を待つことはできず、裁判所が違憲を宣言することによって直ちにその適用を排除しなければならない。しかし、本件規定については、現在まだその段階に達しているとは考えられない」と社会情勢などによっては違憲となる可能性も認めると考えられる意見も含めて、5名の裁判官の補足意見が付される結果となっています。
そして、この最高裁判所決定以後も、2000年1月27日、03年3月31日、04年10月14日、09年9月30日に言い渡された各判決などにより、1995年の判断を引用した合憲判断が繰り返されましたが、これらの判断にも反対意見や補足意見が付されており、2004年10月14日の判決などは、5名の裁判官中2名の反対意見が付される僅差の合憲判決となっていました。
まさに、この婚外子の相続差別の問題は、従来の判断がいつ覆されても、少しもおかしくない、極めて微妙な状況にあったわけです。
今回の判決の内容
以下、ちょっと長いですが、今回の判決の主要な部分を引用してみたいと思います。
相続制度は、被相続人の財産を誰に、どのように承継させるかを定めるものであるが、相続制度を定めるに当たっては、それぞれの国の伝統、社会事情、国民感情なども考慮されなければならない。さらに、現在の相続制度は、家族というものをどのように考えるかということと密接に関係しているのであって、その国における婚姻ないし親子関係に関する規律、国民の意識等を離れてこれを定めることはできない。これらを総合的に考慮した上で、相続制度をどのように定めるかは立法府の合理的な裁量判断に委ねられているものというべきである。この事件で問われているのは、このようにして定められた相続制度全体のうち、本件規定により嫡出子と嫡出でない子との間で生ずる法定相続分に関する区別が、合理的理由のない差別的取扱いにあたるか否かということであり、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、そのような区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、当該区別は憲法14条1項に違反するものと解するのが相当である。・・・・法律婚主義の下においても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては、・・・総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷するものでもあるから、その定めの合理性については、個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され、吟味されなければならない。・・・・昭和22年民法改正以降、我が国においては、社会、経済状況の変動に伴い、婚姻や家族の実態が変化し、その在り方に対する国民の意識の変化も指摘されている。すなわち、地域や職業の種類によって差異のあるところであるが、要約すれば、戦後の経済の急速な発展の中で、職業生活を支える最小単位として、夫婦と一定年齢までの子どもを中心とする形態の家族が増加するとともに、高齢化の進展に伴って生存配偶者の生活の保障の必要性が高まり、子孫の生活手段としての意義が大きかった相続財産の持つ意味にも大きな変化が生じた。・・・さらに、昭和50年代前半頃までは減少傾向にあった嫡出でない子の出生数は、その後現在に至るまで増加傾向が続いているほか、平成期に入った後においては、いわゆる晩婚化、非婚化、少子化が進み、これに伴って中高年の未婚の子どもがその親と同居する世帯や単独世帯が増加しているとともに、離婚件数、特に未成年の子を持つ夫婦の離婚件数及び再婚件数も増加するなどしている。これらのことから、婚姻、家族の形態が著しく多様化しており、これに伴い、婚姻、家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。・・・本件規定の立法に影響を与えた諸外国の状況も、大きく変化してきている。・・・1960年代後半(昭和40年代前半)以降、これらの多くの国で、子の権利の保護の観点から嫡出子と嫡出でない子との平等化が進み、相続に関する差別を廃止する立法がされ、・・・現在、我が国以外で嫡出子と嫡出でない子の相続分に差異を設けている国は、欧米諸国にはなく、世界的にも限られた状況にある。・・・本件規定の合理性に関する以上のような種々の事柄の変遷等は、その中のいずれか一つを捉えて、本件規定による法定相続分の区別を不合理とすべき決定的な理由とし得るものではない。しかし、昭和22年民法改正時から現在に至るまでの間の社会の動向、我が国における家族形態の多様化やこれに伴う国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢及び我が国が批准した条約の内容とこれに基づき設置された委員会からの指摘、嫡出子と嫡出でない子の区別に関わる法制の変化、更にはこれまでの当審判例における度重なる問題の指摘等を総合的に考察すれば、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。・・・以上を総合すれば、遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。したがって、本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。
家族の多様化、社会情勢などを考慮
最高裁判所は、上記決定で、法律婚主義が定着していることを認めながらも、家族の形態の多様化や国民意識の変化、諸外国において嫡出子と婚外子との平等化が進んだことなどを総合的に考慮した上で、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと」は許されないと判断し、民法900条4号ただし書きについて、少なくとも2001年(平成13年)7月時点においては合理性を欠くに至っており、憲法14条1項の法の下の平等に反していたと判断したわけです。
実は、前述した「相続に関する民法改正要綱試案」による改正が見送られた時とは異なり、12年に内閣府が実施した世論調査においては、民法900条4号ただし書きについて現行でよいとするものは35.6%に止まる(1979年調査では47.8%)一方、婚外子が相続できる金額を嫡出子と同じにすべきとするものは25.8%(同15.6%)、どちらともいえないとするものが34.8%(同20.3%)と増加しており、国民感情が明らかに変化していることがみてとれます。また、厚生労働省の人口動態統計によると11年の日本における婚外子の出生率も2.3%(1979年当時0.8%)と大幅に増加しています。
このように時代とともに変遷した国民感情や社会情勢などを総合的に検討した結果、今回の最高裁決定につながったものと考えられます。
遺言書がない場合の相続手続きの流れ
相続が生じた場合に、遺言書があれば、原則として、遺言書の内容に従って遺産が相続されることとなります。それに対して、ご相談者に場合のように、遺言書がなければ、法定相続人が、法律で決められた割合、つまり法定相続分で遺産を相続することとなります。そして、相続人全員で遺産分割協議を行い、当該定められた割合を基にして、具体的な相続財産をどのように分けるかを決めることとなります。しかし、相続人全員で合意できない場合には、家庭裁判所による調停や審判によって、相続財産を分割することになります。
民法900条4号ただし書きは、婚外子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすると規定していますので、今までは、ご相談者の法定相続分はこの規定に従うこととなっていました。しかし、今回、最高裁判所は、民法900条4号ただし書きは憲法14条1項に違反して違憲であると判断し、これを受けて菅官房長官も前述のように「立法的手当ては当然。できる限り対応すべきだ」と述べており、近々、嫡出子と婚外子の相続割合を平等とする法改正が実施されると思われます。ただ、民法が実際に改正されるにはまだ時間がかかるわけですが、その点はどう考えれば良いでしょうか。
この点、最高裁判所判例には事実上の法的拘束力がありますので、現時点で未決着の相続事件や今後発生する相続事件については、今回の違憲判断が適用され、婚外子の相続分も嫡出子と同じとして扱われることとなります。つまり、ご相談者のように、相手方から提示された相続分割の合意書にサインせずに放置していた、すなわち、関係者間の法律関係が確定的なものになったといえる段階に至っていない事案であれば、今回の判断によって違憲無効とされた民法900条4号ただし書きの規定の適用を排除した上で対処することになります。
ご相談者の場合には、今後、遺産分割協議において、本件最高裁の新判断に基づき、嫡出子と同等の相続分を主張することになります。そして、仮に、嫡出子らの他の相続人が反対して合意に至らなかった場合、ご相談者としては、家庭裁判所に調停・審判を申し立てれば、裁判所は、今回の最高裁判所の判断に従って、嫡出子と同等の相続分をご相談者に認めてくれることとなるでしょう。
余談として-遡及しないということ
なお、最高裁判所は、今回の判断の中で、「本決定の違憲判断は、Aの相続の開始時(筆者注:2001年7月)から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない」として、本決定の効力が過去の相続に遡って影響しないとしています。今回の違憲判断が、既に行われた遺産の分割等の効力にも影響して、解決済みの事案に効果が及ぶとすることは、著しく法的安定性を害することとなるためです。
具体的に言えば、既に決着済みの事案につき、従来の相続の枠組みに従って法定相続分を差別的に取り扱われた婚外子が遺産分割のやり直しを求めたり、さらには、相続後に第三者の手に渡った相続財産の取り戻しを求めたりするような動きが多発して混乱を招く結果となることを防止するための措置と考えられています。
しかし、従前の制度の枠の中で、差別的な取り扱いを甘んじて受け入れてきた婚外子も多数存在するわけであり、混乱を避けるという最高裁判所の考え方に合理性があるとしても、この判断部分にはやりきれない思いを抱いた婚外子も大勢いると思われ、今後の国会での法改正での議論にも影響を及ぼしそうです。