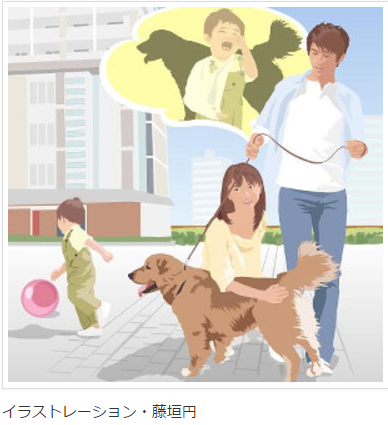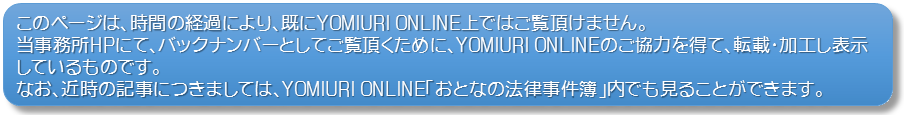愛犬が他人に怪我をさせた…飼い主の責任は?
相談者 F.Mさん
私たち夫婦は自宅のマンションで大型犬を飼っています。
近くにはちょっとした森林公園があって休日には必ず犬と一緒に散歩に出かけます。大型犬といっても、性格は穏やかでめったなことでは
ところがある日、妻が「ねえ、これを見て」と言いながら週刊誌を持ってきました。見ると、芸能人夫妻が自宅マンション内で飼っていたドーベルマンが、隣人に
また、逆に飼い犬が他人の不法行為によって被害を受けた場合の損害賠償はどうなっているのでしょうか。ネットで調べたら、ペットは、法律上は「物」として扱われると書いてありましたが、私たち夫婦にとっては、我が子同然であって、仮に突然の交通事故などで死んでしまったら、大変な精神的ショックを受けることと思います。そのような場合、加害者に慰謝料などを請求することはできるのでしょうか。
(回答)
芸能人の飼い犬による事件が話題に
相談者も週刊誌で読んだとのことですが、2013年10月10日、俳優の反町隆史さんと女優の松嶋菜々子さん夫妻の愛犬であるドーベルマンが、同じマンションの住人に咬みつき、住人が転居したため賃料収入を失ったとして、都内のマンション管理会社が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は夫妻側に1725万円の支払いを命じました。同年5月言い渡された第一審判決では385万円だった賠償額が、一気に4倍以上に跳ね上がったことになります。
この事案は、実際に咬まれて
今回は、自分の飼い犬が事件を起こした際に、その飼い主がどのような責任を負うのかを中心に説明していきたいと思います。
飼い犬が第三者に損害を与えた場合に関連する法律
まず、皆さんもよくご存じの「動物の愛護及び管理に関する法律」(いわゆる「動物保護法」)第7条が、「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体
ただ、この規定は、動物の飼い主に対し、動物が人の生命、身体、財産に害を加え、迷惑となる行為をさせないようにする努力義務を定めているに過ぎません。
現実にペットである飼い犬が第三者に損害を与えた場合に問題となってくる主な法律としては、民法第718条1項を挙げることができます。同法律では、「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」と規定しており、飼い犬が他人に危害を加えた場合、動物の占有者である飼い主が損害賠償責任を負うと明記しているわけです。他面、飼い主が十分に注意を払った場合にまで責任を負わせるのは酷であることから、同条ただし書きにおいて、「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない」と規定しています。逆に言えば、ペットの飼い主は、「相当の注意」を払ったことを立証しない限りは、損害賠償責任を負うことになるわけです。
ちょっと難しい話になりますが、一般的な不法行為に基づく損害賠償責任の場合には、加害者の過失の立証責任は被害者が負う(被害者が加害者に落ち度があったことを証明しなければならない)ことになっているのですが、ここで問題となっている民法第718条に基づく損害賠償責任の場合には、被害者がペットの飼い主の過失を立証するのではなく、ペットの飼い主が「相当の注意」を払ったことを自ら立証しなければ責任を免れないとされているのです。
つまり、例えば誰かが飼っているペットに咬まれるなどの被害を受けた被害者は、単に自分に損害が発生したことを主張していけば良いのであり、あとはペットの飼い主の方で、相当の注意を払ったことを立証しないと責任を免れないということです。法律上、動物の飼い主には、通常より重い責任が課されているわけです。
飼い主が責任を負わずに済む場合
ここでいう「相当の注意」とは、どの程度の注意義務だと考えれば良いのでしょうか。
この点、最高裁判所は、「通常払うべき程度の注意義務を意味し、異常な事態に対処しうべき程度の注意義務まで課したものでない」(昭和37年2月1日)としており、「その動物の種類性質および周囲の情況に照らし、その際採った占有者の具体的処置は相当であったかどうかによって決定せられる」(大阪地方裁判所・昭和41年11月21日)としています。
「相当の注意」をもって保管していたか否かは、<1>動物の種類・雌雄・年齢<2>動物の性質・性癖・病気<3>動物の加害前歴<4>飼い主につき、その職業・保管に対する熟練度・加害時における措置態度<5>被害者につき、警戒心の有無、被害誘発の有無、被害時の状況といった事実関係をもとに、個別的・具体的に判断されることとなります。
例えば、飼い主が「相当の注意」をもって管理していたとして、損害賠償責任が否定された裁判例として、通り抜けのできない空地上の物置の横に2メートルの鉄鎖で
つまり、人の出入りのほとんどない場所に繋留されていたとしても、咬傷事件が発生した以上は、被害者の自招行為に基づくものでない限り、飼い主として「相当の注意」を払っていたとして責任を免れることができないことも考えられるわけです。いわんや、上記事案とは異なり、散歩中の咬傷事件の場合には、人との接触の機会がより多くなる上、常に飼い主の管理の下に置かれていることから、より高い注意義務が要求されることになると思われます。
そして、飼い主について、免責事由を簡単には認めないのが、最近の裁判の傾向であり、飼い主の責任はほとんど無過失責任に近いものとも言われています。
飼い犬が咬みついた場合の損害
飼い犬が人に咬みついて怪我をさせた場合には、上述のとおり、飼い主が「相当の注意」をもって管理していたと認められない限り、飼い主は被害者に対し、治療費や慰謝料などの損害を賠償しなければならないことになります。請求できる損害の内容については、交通事故と同様に考えることができると思われますが、具体的に言うと、例えば、<1>治療費(必要かつ相当な範囲での実費)<2>その他治療関係にかかった費用(医師の指示がある場合の特別室使用料等)<3>通院にかかった交通費など<4>休業損害<5>精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料<6>壊された物がある場合の修理費などを賠償しなければならないことになります。
飼い犬が吠えただけでも損害賠償責任が発生
飼い犬による事故としては、上記のように、誰かに咬みついて怪我を負わせることが一般的と思われますが、被害者が吠えかかってきた犬に驚いて転倒し怪我をするような場合も想定されます。このような場合でも、飼い主は損害賠償責任を負うのでしょうか。
この点、飼い主として賠償すべき損害の範囲は、不法行為と相当因果関係にある全ての損害であり、そのような不法行為があれば一般的に生じるであろう損害であるとされています。散歩で通りかかった犬が突然1回吠えたことに驚いて転倒し、歩行者が骨折した事案でも、「犬の行為としては、単に1回、原告に対し、吠えたというにすぎず、原告に飛びかかろうとしたことはない。しかしながら、本件犬が原告に向かって吠えたことは、原告に対する一種の有形力の行使であるといわざるを得ず、犬の吠え声により、
なお、この裁判例において、飼い主は、「飼い犬を散歩に連れ出す際、飼い犬が吠えないようにする注意義務は、社会通念上、動物の占有者に課されてはおらず、神奈川県動物保護管理条例も散歩において、犬が吠えることを禁じていないし、また、この制御を飼育者に要求することは甚だ酷と言わなくてはならないから、本件犬の保管に過失はない」と主張しました。これに対し裁判所は、「なるほど、犬は、本来、吠えるものであるが、そうだからといって、これを放置し、吠えることを容認することは、犬好きを除く一般人にとっては耐えがたいものであって、社会通念上許されるものではなく 犬の飼い主には、犬がみだりに吠えないように犬を調教すべき注意義務があるというべきである。特に、犬を散歩に連れ出す場合には、飼い主は、公道を歩行し、あるいは、
飼い主は飼育から生じる一切の責任を負担?
この裁判では、さらに「私法上の不法行為の過失の有無の判断は、神奈川県動物保護管理条例に拘束されるものでないから、被告が右条例を
ちなみに、閑静な住宅地で犬の鳴き声で騒音被害を受けたとして提起された訴訟でも、「住宅地において犬を飼育する以上、その飼い主としては、犬の鳴き方が異常なものとなって近隣の者に迷惑を及ぼさないよう常に飼犬に愛情を持って接し、規則正しく食事を与え、散歩に連れ出し運動不足にしない、日常生活におけるしつけをし、場合によっては訓練士をつける等の飼育上の注意義務を負うというべきであるところ、被告らの飼い犬が一項で認定したような異常な鳴き方をしている事実からすると、被告らは、右の注意義務を怠ったものといわざるをえない」として、犬の飼い主に対し損害賠償請求を命じています(東京地方裁判所・平成7年2月1日)。
俳優夫妻のケースでは
冒頭で指摘した、俳優夫妻のケースは、夫妻の愛犬・ドーベルマンが同じマンションの住人に咬みつき、住人が転居したため賃料収入を失ったとして、都内のマンション管理会社が損害賠償を求めた事案です。この事案は、咬傷事件の直接の被害者ではない賃貸人が、被害者が退去したことで得られなくなった賃料収入の逸失利益および被害者から徴求を免除した解約違約金について損害賠償請求したというものです。
第一審の東京地方裁判所は、賃料収入の逸失利益については相当因果関係が認められないとして損害賠償請求を認めずに、解約違約金についてのみ、損害賠償請求を認めました(平成25年5月14日判決)。賃料収入の逸失利益については間接損害であり、間接損害については、原則として相当因果関係が認められず、直接の被害者と損害賠償請求をする者とが経済的に一体関係にあると認められる場合に限って相当因果関係が肯定されるところ、本件においては、咬傷事件の被害者と賃貸人との関係は経済的に一体であるとは言えないことから、相当因果関係を認めなかったものです。一方、解約違約金については、被害者が咬傷事件によって精神的ショックを受けて退去せざるを得なくなったため支払い義務が生じた解約違約金を管理会社が免除したものであり、反射的損害と言えるものであるから、385万円の損害賠償請求を認めたものです。
これに対して、控訴審の東京高等裁判所(平成25年10月10日判決)は、居室でのみ飼育できる小動物を除き、動物を飼育することを禁止している建物使用細則に違反して動物を飼育し、飼育する動物がマンションの区分所有者、居住者その他の関係者の生命、身体、財産の安全を確保し、快適な住環境を保持するというマンションの区分所有者、居住者その他の関係者の共同の利益を侵害する行為をして専有部分の区分所有者その他の権利者の有する財産上の利益を侵害し、民法第718条1項及び第709条により損害賠償責任を負うべきときは、上記共同利益が侵害されて財産上の利益を侵害された者は不法行為の直接の被害者に当たるものと解するのが相当であり、動物に咬みつかれた被害者の間接被害者に当たると解するのは相当ではないとして、賃料収入の逸失利益についても損害賠償請求を認めたため、第一審の4倍の損害賠償金額となったものです。
この事案からも明らかなように、ペットの飼い主は、事案によっては、非常に重い責任が課されることにもなりかねませんので、ペット、特に人を傷つける可能性のある動物を飼う際には、十分覚悟して、責任をもって飼育することが必要となるわけです。
ペットが被害を受けた場合
本相談とは直接の関係はありませんが、逆にペットが他人の不法行為によって被害を受けた場合の損害賠償はどうなるのでしょうか。例えば、飼い犬が散歩中に交通事故にあって死んだり、怪我を負ったりしたような場合です。
飼い犬などのペットは、通常の自動車保険では財物、つまり「物」として扱われますので、対人賠償保険から治療費や慰謝料を受けられず、対物賠償保険から補償を受けることになります。この場合の補償ですが、あくまで「物」ですので、時価が原則となります。つまり、飼い犬が交通事故で死亡した場合には、その時価相当の賠償、怪我をした場合には、時価を上限に治療費が支払われることになるわけです。ここでいう時価は、血統書などによる客観的な判断によるわけですが、通常は購入代金額を上限に考えられるでしょうから、10万円で購入した犬が交通事故で怪我をして治療費が30万円かかったとしても、原則として10万円が補償の上限ということになると思われます。
しかし、相談者も述べているように、ペットを家族同然と考える人も多く、ペットを「物」と考える考え方に納得できず、時価以上の治療費や慰謝料などを請求して裁判となる事例も増えてきているようです。
名古屋高等裁判所・平成20年9月30日判決では、購入額6万5000円の飼い犬が交通事故で怪我をした事例において、「一般に、不法行為によって物が
また、同判決では、慰謝料についても、「近時、犬などの愛玩動物は、飼い主との間の交流を通じて、家族の一員であるかのように、飼い主にとってかけがえのない存在になっていることが少なくないし、このような事態は、広く世上に知られているところでもある(公知の事実)。そして、そのような動物が不法行為により重い傷害を負ったことにより、死亡した場合に近い精神的苦痛を飼い主が受けたときには、飼い主のかかる精神的苦痛は、主観的な感情にとどまらず、社会通念上,合理的な一般人の被る精神的な損害であるということができ、また、このような場合には、財産的損害の賠償によっては慰謝されることのできない精神的苦痛があるものと見るべきであるから、財産的損害に対する損害賠償のほかに、慰謝料を請求することができるとするのが相当である」とし、飼い主の夫婦に各々20万円の慰謝料が相当と判示しています(ただし、飼い主側にも過失があったとして、1割の過失相殺を認めています)。
この事例は、飼い主夫婦には子供がおらず、飼い犬を我が子のように思って愛情を注いで飼育していたものであり、飼い犬は、飼い主との交流を通じて、家族の一員であるかのように、飼い主夫婦にとってかけがえのない存在になっていたものと認められた事例です。
このように、事情によっては、購入費を上回る治療費や慰謝料が認められる場合もありますので、不幸にもこのような事態に遭遇してしまい、物としての賠償ではどうしても納得いかないという場合には、訴訟も含めた法的手段を検討する余地はあるということです。