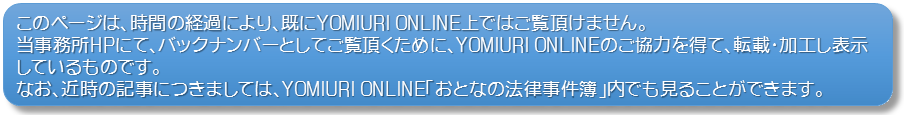民法の大改正、ポイントを教えて
相談者 Y.Kさん
私は大手メーカーに勤務する34歳のサラリーマン。趣味のテニスを通じて会社の外にも友人がたくさんおり、頻繁に飲み会に誘われます。
つい先日の話です。地酒のおいしい店に4、5人で集まって飲んでいたのですが、友人のMがかばんから雑誌を取り出し、「おい、こんな話、知っているか」と問いかけてきました。Mはトレンド情報をいち早くキャッチする男なので、みんな身を乗り出して、記事を見てみると「民法120年ぶりの大改正」などと書いてあります。
記事によれば、飲み屋のツケ払いの時効が1年から5年になるとか、借金の保証人が今まで以上に保護されるようになるとか、法定利率というものが年5%から年3%に引き下げられるとか、借りているアパートの敷金が全て戻ってくるとか、改正の内容は多岐にわたるようです。その時の飲み会でも「オレのツケはチャラにはならないのか?」「そういえば大学時代の友人が借金の保証人になって苦労しているって言っていたなあ」「敷金が全部戻ってくるんなら結構な額になるぞ」などと、みんなが口々に言い出し、大いに盛り上がりました。大改正の行方は私のようなサラリーマンにも無関係とはいえないようで、それ以来、新聞は注意して読むようにしています。
ただ、制定から120年もたったのに、なぜ今になって改正されるのかがよく理解できません。それに、変更点が色々ありすぎて、ポイントもよく分かりません。この点を分かりやすく説明してもらえないでしょうか。
なお、以前このコーナーで取りあげられた「自分の利用履歴が規約変更で知らないうちに他社へ…許される?」(2014年7月23日)では、民法の改正で、約款に関する明文規定が盛り込まれるようなことが書かれていましたが、飲み会の時に見た雑誌には、改正内容の中に約款のことは載っていませんでした。約款に関する改正はなくなったのでしょうか?(最近の事例をもとに創作したフィクションです)
(回答)
民法の大改正がいよいよ実現
民法の大改正がいよいよ年内に実現しそうです。1896年の現行民法制定以来、120年ぶりの改正とあって、様々なメディアで特集が組まれるなど、話題となっています。その内容は、相談者も指摘するように、極めて多岐にわたっており、「飲み屋のツケから逃げられない」「損害保険の保険金受取額が増加」「保証人の原則禁止」「敷金は原則返還」「認知症の高齢者が交わした契約は無効」など、一般のサラリーマンにも大きな影響がありそうです。
この改正の発端は2009年10月の法務大臣からの諮問にあります。当時の千葉景子法務大臣(弁護士出身)が、「民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい」と、民法改正を法制審議会に諮問し、同年11月から法制審議会民法(債権関係)部会において、民法のうち債権関係の規定について、契約に関する規定を中心として見直しが開始されたわけです。13年2月26日開催の同部会第71回会議では「民法(債権関係)改正に関する中間試案」が決定され、パブリック・コメントの手続きを経てさらなる審議が行われ、14年8月26日に開催された同部会第96回会議において、「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が決定されて、同年9月8日に法務省から発表されるにいたりました。法務省は、今年2月ごろに予定される法制審議会の答申を受け、今年の通常国会への法案提出を目指しているということです。
国民一般に分かりやすい民法へ
民法は、私たち市民生活の最も基本的なルールを定めている法律です。普段あまり意識していませんが、例えば、コンビニでおにぎりを買うという行為は、民法では「売買契約」が締結され履行されたと評価されるように、私たちの生活に密接に関係している法律なのです。前述のように、民法は1896年に制定され、2年後の98年7月に施行されました。それ以来約120年の間に、市民生活や経済環境は大きく変化しましたが、成年後見制度の導入などの部分的な改正がなされただけで、債権関係の規定については、ほとんど改正が行われてきませんでした。そこで、<1>社会・経済の変化に対応させる、<2>判例法理をふまえて規定を明確化することにより、国民一般に分かりやすいものとするといった観点から、民法を大改正することになったのです。
現段階における要綱仮案に掲げられた民法の改正点は約200項目にも及びますが、私たちの生活に影響のある項目や、メディアで頻繁に取りあげられている項目を中心に、以下、主だった改正点を確認しておきたいと思います。
短期消滅時効の廃止
この点が、本改正で、一番メディアなどで取りあげられ、話題になっているところかと思います。「飲み屋のツケから逃げられない」といった刺激的な見出しは、サラリーマンの興味を引きつけるに十分です。
消滅時効とは、一定期間の経過によって、債権等の財産権が消滅する制度のことで、例えば知人にお金を貸した場合、返済を約束した時から10年間が経過すると、お金を返してくれとは言えなくなってしまいます。これは、民法で、お金を貸した場合などのような、一般的な債権の消滅時効期間が、「権利行使できる時から10年間」と決められているためです。
しかし、現行の民法では、上記以外に、職業別に「短期消滅時効」というものが定められています。例えば、飲食店の料金の時効は1年間、小売業の商品代金の時効は2年間、弁護士報酬の時効は2年間、医師の診察料の時効は3年間などと規定されているのです。つまり、行きつけの小料理屋で、ツケで飲んだ場合、飲食店の料金の時効は1年間ですから、1年間経過すれば、お店からツケを支払ってほしいと言われても、時効を理由として払わなくてもよいことになるのです。
ちなみに、民法第174条は「次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する」として、4号に「旅館、料理店、飲食店、貸席
ただ、同じようにお金を払ってくれと求める権利なのに、なぜ、相手の職業や業種などによって、時効期間が異なるのかの根拠は不明です(フランス民法に由来すると言われています)。民法制定当時は何らかの合理性があったのかもしれませんが、現代社会で、相手の職業などにより、これほどまでに時効期間が異なる理由を説明することはもはや困難です。例えば、弁護士報酬は2年間で時効になるのに対し、同じ「士業」といわれる税理士や司法書士等の報酬の時効期間は、民法に規定されていないことから、一般的な債権と同様10年間とされているなど、具体的に不合理な点も指摘されています。そこで、今回の改正では、職業別の短期消滅時効が廃止され、消滅時効期間は、「権利行使できる時から10年」という従来の一般原則に加えて、「権利行使できると知った時から5年」の時効期間が追加されたわけです。
改正後は、小料理屋においてツケで飲んだ場合、原則として1年ではなく5年経過しないと消滅時効にかからないことになってしまうわけです。これをもって、世間では民法改正によって「飲み屋のツケから逃げられない」と言っているわけです。
法定利率の引き下げ
法定利率とは、「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借りのことです)で金利を定めない場合や支払いが遅れた場合に支払う遅延損害金などに適用される金利のことであり、民法では年5%の固定性とされています。この数字は、民法制定当時の欧州諸国の法定利率や平均的な貸出金利などを参考に定められたと言われています。
要綱仮案では、法定利率を3%に引き下げ、その後3年ごとに1%刻みで見直す変動制に改正するとされています。現行の5%という利率は1896年の民法制定以来変更されていませんが、長期金利の指標となる新発10年物国債の利回りは0.275%(2015年1月10日引値)、国内銀行の新規平均貸出約定総合金利も0.932%(14年11月分:日本銀行金融機構局発表)まで低下している現状の市場環境とは、大幅にかい離していると従来から指摘されてきました。銀行の大口定期預金の金利が0.1%に届かない時代であり、今時、年5%の利回りの金融商品など探すのが大変ですが、お金を貸したのに返してくれなかったような場合、返済がなされるまでの間、相手に対して年5%分もの利息を請求できることになるわけです。
私も、金銭の未払い案件で、債務者に対して支払いを求める裁判を提起する時などは、5%という超高金利の定期預金にお金を預けていると思えば良いですよ、などとクライアントに冗談でよく話していたくらいです(もちろん相手に支払い能力があることが前提ですが……)。
損害保険の保険金受取額が増加
なお、法定利率が引き下げられても、私たちの生活にはそれほど大きな影響は出ないのではないかと思われるでしょうが、意外なところで影響が出ると言われています。それが、冒頭で述べた、損害保険の保険金受取額が増加するという点です。交通事故などで死亡したり、重度の後遺症が残ったりした場合などに支払われる損害保険の保険金が、法定利率が下がると増えることになるのです。
損害保険では、死亡したり、重度の後遺症が残ったりした場合に、交通事故などに遭わなければ得られたであろう給料等の収入を逸失利益として算定し、損害保険金に反映しています。逸失利益は、交通事故発生の前の年の収入から、生活費を控除した金額に対し、交通事故等に遭わなければ働けたであろう年数(就労可能年数)を乗じて計算されますが、就労可能年数が例えば40年であったとしても単純に40を乗じるわけではありません。損害保険金を前もって一括で受け取ることになるため、就労可能年数に複利で運用した場合の利益が差し引かれることになるのです(中間利息の控除と言います)。そして、この中間利息の控除には、民法上の明文規定はありませんが、判例によって法定利率が使われているのです。簡単に言えば、例えば1年後にもらうべき金銭を、今もらった場合、その1年間に運用できた分の金銭をあらかじめ差し引いて渡すということであり、その際の運用益(元金に対する割合)を大きく想定すれば、それだけ、もらえる金額は減少することになります。
最高裁判所・平成17年6月14日判決は、「民法404条において民事法定利率が年5%と定められたのは、民法の制定に当たって参考とされたヨーロッパ諸国の一般的な貸付金利や法定利率、我が国の一般的な貸付金利を踏まえ、金銭は、通常の利用方法によれば年5%の利息を生ずべきものと考えられたからである。そして、現行法は、将来の請求権を現在価額に換算するに際し、法的安定及び統一的処理が必要とされる場合には、法定利率により中間利息を控除する考え方を採用している……損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するについても、法的安定及び統一的処理が必要とされるのであるから、民法は、民事法定利率により中間利息を控除することを予定しているものと考えられる。このように考えることによって、事案ごとに、また、裁判官ごとに中間利息の控除割合についての判断が
想定した利率が低い方が差し引かれる分の運用益が少なくなるわけですから、法定利率が下がると算定される逸失利益が増え、したがって受け取る損害保険金も増えることになります。日本損害保険協会が試算したケースでは(27歳男性で全年齢平均賃金が41万5400円、就労可能年数40年、一家の柱で被扶養者が2人=生活費控除割合35%=いる場合)、法定利率が現行の5%のままであれば逸失利益は5559万7219円であるのに対し、法定利率が3%に引き下げられると逸失利益は7489万5374円と1929万8155円(25.3%)も増えることになります。もちろん、交通事故になど遭わないにこしたことはありませんが、仮に事故の被害に遭ってしまった場合、受け取る損害保険金が増えるのですから、事故の被害者への影響は大きいかもしれません。
しかし、報道などによれば、必ずしもプラスの面ばかりではないかもしれません。自動車保険などに加入する人が支払う保険料が上昇するのではないかと懸念されているからです。法定利率の引き下げにより、損害保険会社が支払う損害保険金が増加するのですから、損害保険会社にとってはコスト増の要因になります。保険料は保険金の支払額だけで決定されるものではありませんが、保険料が上がる一要素になることは間違いありません。自家用車をお持ちの方には気になるところです。
保証人の保護の強化
「事業をしている友人から頼まれて借金の保証人となったが、友人が行方不明になってしまい、とても支払うことのできない多額の債務の弁済を求められて困っています。破産するしかないでしょうか」というような相談を受けることがあります。最近は見かけませんが、かつて多重債務が社会問題化した際には、事業を営む父親の借金について、子どもやその配偶者はもちろん、親戚や友人といった人までが連帯保証をして、その事業が破綻すると、それに伴って、十数人が一度に自己破産するというような悲惨なケースもありました。
こうした保証人になったことによる被害は、今でもよく聞かれます。特に企業向け融資の保証人となった場合、保証人の負担は大きくなってしまいます。
そこで、今回の民法改正では、当初、<1>企業向け融資における保証人の保護、<2>第三者による連帯保証の原則禁止という方向で議論が始められました。しかし、第三者による連帯保証が原則禁止とされると、中小企業が金融機関から融資を受け
本改正にあたって「保証人の原則禁止」という言葉を見かけますが、上記の内容からすれば、むしろ、「禁止」という言葉より「制限」などと表現した方が的確かもしれません。
なお、保証に関しては、他にも例えば「友人から開業するので店を借りる際の保証人になってくれと頼まれ、どうせ支払うことになっても100万円くらいだろうと軽い気持ちで引き受けたら、友人が家賃を滞納したまま行方不明になってしまい、滞納家賃や原状回復費用として1000万円も請求された」という話もよく聞かれます。民法の規定では、一部の債務を除いて、保証人が負担する限度額を定める規定がおかれていないため、保証人が思わぬ金額の弁済を求められることがあり得るわけです。
この点、要綱仮案では、保証人保護の観点から、個人保証の場合には債務の内容にかかわらず、事前に極度額(保証する金額の上限)を定めなければならないとしています。上述の不動産を借りる際の保証人になる場合にも、この改正によって、保証契約を締結する前に保証金額の上限を、例えば100万円などと定めておけば、突然、自分が想定していた金額をはるかに超えるような金額の請求を受けるような事態にはならないわけです。
敷金は原則返還
マンションなどを賃貸する場合、家賃の1~3か月分程度の敷金が必要となることが多いですが、退去時に敷金が全く返ってこなかったり、ハウスクリーニング、クロス張り替え、畳表替えなどの原状回復費用として敷金以上の金額を請求されたりするトラブルが多く発生しています。独立行政法人国民生活センターには、敷金や原状回復に関するトラブルに関する相談が、2012年には1万4212件、13年も1万3916件寄せられているということです。
敷金に関しては、民法には規定がなく、国土交通省が制定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」があるものの、
そこで、要綱仮案では、敷金を「賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」と明確に定義付けた上で、「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」は、「賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない」として、敷金の返還義務を規定しています。
また、最高裁判所・平成17年12月16日判決が、「賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払いを内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払いを受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになる」と判示しているように、判例では、通常の使用をした場合に生ずる劣化や通常損耗は原状回復義務には含まれないとされています。この点は、本コーナー「賃貸マンション退去時の補修費用、誰が負担?」(2012年2月8日)をご参照頂きたいと思います。
要綱仮案は、「賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に回復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない」として、原状回復義務について、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」と判例で示されていた内容を明確に規定することとなっています。
認知症の高齢者が交わした契約は無効
意思能力のない者がした契約が無効であるというルールは、民法の条文には明記されていないものの、近代法の大原則として当然に認められています。意思能力とは、法律用語辞典などをみると、「法律関係を発生させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断、予測できる知的能力。一般には、幼児、重度の知的障害者、泥酔者などは意思能力がないとされている」などと書かれています。
重篤な認知症の高齢者も、ここに含まれることになりますが、超高齢社会(65歳以上の高齢者が人口に占める割合が21%を超えた社会)を迎えて、上記意思能力に関するルールが重要となる中で、民法に明文規定がないのはおかしいということで、契約の当事者が意思能力を有しなかったときは、その契約は無効とする旨の規定を新設することになりました。つまり、従来と何も変わらないのですが、国民一般に分かり
購入商品に問題があった場合の責任
インターネットを通じて購入した商品が故障していた場合、民法では、売買契約を解除する、損害賠償を請求するという2つの方法が規定されています。要綱仮案では、この2つの方法に加え、「目的物の修補」の請求、「代替物の引き渡し」の請求、「代金の減額」の請求が規定されています。ネット市場での売買が一般化し、商品の現物を見ないで購入するケースが増えていることに対する措置と考えられています。
なお、要綱仮案では、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」としています。民法で使用されている「
その他
要綱仮案における改正点は約200点あり、まだ他にも改正点は多数あります。興味のある方は、法務省のHP(ホームページ)に掲載されている「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」をご覧になって頂ければと思います。
約款について
さて、ここまで、今回の民法改正でメディアによく取りあげられている事項などを紹介してきましたが、相談者の指摘のとおり、要綱仮案では、「約款」に関しては盛り込まれませんでした。
要綱仮案が決定された法制審議会民法(債権関係)部会第96回会議に提出された際には、定型約款の定義、定型約款によって契約の内容が補充されるための要件等、定型約款の内容の開示義務、定型約款の変更等の定型約款に関する規定が記載されていたのですが、意見がまとまらず、結局、保留として引き続き検討されることとなったのです。
約款はインターネット通販など、多くの契約の際に用いられ、私たちの生活にも深く関係しています。約款を作成して契約の場面で使用している企業としては、大量の取引を安全かつ効率的に行う重要な手段となっている一方、消費者としては約款を読んでいなかったために不利益を被る場合もあり、トラブルも生じています。そして、民法には、約款に関する明文規定がなかったことから、消費者保護を図るという観点から、今回の改正で明文化しようという動きがありました。しかし、経済団体からの推薦委員が反対したため仕切り直しとなったとの報道がなされています。
日本経団連は、民法改正中間試案で約款に関する規律を設けることが提案されていることに対して、「中間試案では、約款に関する一連の規律を設けることを提案しているが、疑問である。そもそも、現実の紛争は個々の条項の当否という実質内容に関して発生すること、約款の拘束力という形式面も、個別・具体的な利用実態を総合判断せざるを得ないことについては、現在と全く変わりがない。むしろ、十分な立法事実がない中で、約款に関する一連の規律を新設することは事実上の規制強化に他ならず、有形・無形のコスト増加によって、自由で健全な事業活動を必要以上に阻害しかねず、一般法たる民法の役割を大きく踏み外すおそれがある。すなわち、企業は経済社会の要請に応じて、より安価で高品質の商品・役務を迅速かつ効率的に提供することが消費者の利益に
この点については、国会への法案提出までに、約款に関する議論は再燃する可能性があるのではないかとも言われており、推移を見守りたいと思います。