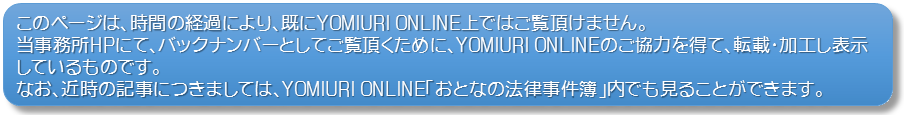斜線引いた遺言書が無効って本当? 有効な遺言書の作り方教えて
相談者 T.Kさん
父が先日亡くなりました。長年、開業医として自宅兼診療所で働いてきた人です。大きな病院が近くにないので、地元の人には頼りにされていたようです。そんな姿を見て育った兄も医者になり、父と2人で診療所を切り盛りしていました。私は3人きょうだいの末っ子。兄の2つ下に姉がいます。私は東京の女子大を出た後、都内で働き、2年前に結婚しました。姉もすでに結婚して独立しています。
父は地元で名士と言われる家に育ったせいでしょうか、とても厳格で娘には近寄りがたい存在でした。4年前に母が亡くなってからは、ますます気難しくなり、会うのはお正月に帰省した時だけになっていました。父が体調を崩した後も、何となく兄にまかせきりだったことが、今になって悔やまれます。
葬儀もつつがなく終わり、きょうだい3人がそろった時に貸金庫を開けることにしました。中から出てきた遺言書には、全ての財産を兄に渡すと書かれていました。晩年のことを考えると、その内容は予想したもので驚きはありませんでしたが、ただ、不思議なことに、文字の上から赤色のボールペンで大きく斜線が引かれています。兄は、「父の面倒を見て診療所の経営も手伝っていた自分がすべての財産をもらい受けるのは当然であり、父もそのような話をしていた」と言っています。斜線が引かれていることについては、「遺言書には変わりなく、書かれている文字も十分読めるのだから、遺言の効力に問題はない」と主張しました。
私も姉も、父の面倒を兄に押しつけてきたこともあり、兄の言い分も理解できなくはないのですが、自分の取り分が全くないというのは釈然としません。それに、遺言書があるといっても斜線が引かれているということは、父は一度遺言書を作ったあとに翻意したのではないかという疑念もあります。私はどのような主張ができると考えられますか。
なお、この際、私自身の問題も相談したいと思います。私と夫との間に子どもはいません。夫に万一のことがあった場合、相続財産はすべて自分のものになると安易に思っていましたが、先日何げなく見ていたテレビでは、子どもがいない夫婦の場合、夫がきちんと遺言書を作っていないと大変なことになると言っていました。その大変なことというのはどういう意味でしょうか。ちなみに、夫の両親は既に亡くなっていますが、夫の3人の兄弟は健在です。また、夫に遺言書を作ってもらっても、父のケースのように有効性に疑念が残っては争いのもとになります。遺言書の正式の作り方についても教えて下さい(最近の事例をもとに創作したフィクションです)。
(回答)
遺言書に関する最高裁判所の判断が話題に
平成27年(2015年)11月20日、最高裁判所第2小法廷は、赤色の斜線が引かれた遺言書の効力が争われた訴訟の上告審で、遺言書を有効とした広島高等裁判所の判決を破棄し、無効とする判決を言い渡しました。
報道によると、原告の女性の父親は、生前、自宅や経営していた病院の土地・建物や預金など、財産の大半を長男に相続させるとする自筆の遺言書を作成していました。父親の死後に、その遺言書が病院の金庫から見つかりましたが、遺言書は用紙1枚で、自筆遺言証書の要件は充足していましたが、文面の左上から右下にかけて赤色のボールペンで斜線が引かれていたことから、原告の女性が、遺言書は破棄されたものであるから無効だと主張し、遺言無効確認訴訟を提起したということです。
この判決は新聞などで大きく取りあげられましたが、それを見た人は、文書に斜線が引いてあるなら無効になるのは当然で、なぜ、広島高等裁判所がその遺言書を有効としたのか分からないという印象を持ったかも知れません。
確かに、書面上で、左上から右下にかけて赤で斜線が引かれていたら、その書面を破棄したという意味に受け取るのが通常だと思います。ただ、このように高等裁判所と最高裁判所で判決が分かれたのは、遺言書作成に関する、民法の厳格な姿勢に原因があります。
裁判所の判断が分かれた原因
この問題を理解するためには、まず、遺言書に関し、民法に次のような規定があることを知る必要があります。
(民法968条2項)
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(民法1024条)
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
上記民法1024条の「破棄」には、焼却・破り捨てなど、遺言書の形状を破壊する行為、黒く塗り潰して内容を判別できない程度にする行為などが含まれると考えられます。他方、遺言書を「変更」するためには、民法968条2項に記載されているような一定の厳格な要件が求められています。
そこで、本件で問題となっている斜線のように、遺言書の文面が読める状態である場合には、1024条の「破棄」に当たるとして、遺言が撤回されたと考えるのか、
各裁判所の判断内容
原審である広島高等裁判所は、「本件斜線が引かれた後も本件遺言書の元の文字が判読できる状態である以上、本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は、民法1024条前段により遺言を撤回したものとみなされる『故意に遺言書を破棄したとき』には該当しない」として、遺言書は有効と判断しました。
それに対して、最高裁判所は、遺言書は無効と判断し、次のように判示しています。
「民法は、自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について、それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には、968条2項所定の厳格な方式を
従来からの争いに決着
今回の最高裁判所の判決では、条文に忠実とも言える、民法968条2項の適用を前提とする見解に対して一定の理解を示しながらも、「赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして、その遺言書の全体を不要のものとし、そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である」と、社会一般の考え方に従って、遺言を撤回したものと判断したわけです。
今回の最高裁判所判決に関しては、遺言書作成者の意思を尊重するものとして、好意的に受け止める向きが多いようです。ただ、今回の事例では、遺言書作成者が自ら斜線を引いたこと自体は争われませんでしたが、今後も、同種の事案が出てきた場合には、斜線を引いたのが誰かが争われることも考えられますから、この種の遺言書についての争いが全て解消したというわけではないと思われます。
いずれにしても、今回の遺言書を作成した方の真意は不明ですが、仮に遺言書を本当に撤回するつもりなら、遺言書に関する法的規制をきちんと確認し、専門家のアドバイスを聞くなどして、争いが生じる可能性があるような手段をとらなければ、子供同士が遺言書の有効性を巡って裁判で争うようなことにはならなかったわけです。
そこで、こういった紛争を回避するためにも、以下、遺言書作成の基本について説明したいと思います。
遺言書を作成する意義
後述の通り、公正証書による遺言を除いて、遺言書については、家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。司法統計によれば、2014年の検認件数は1万6843件と、その10年前(04年1万1662件)の約1.44倍に増加しています。同様に、公正証書遺言の作成件数は10万4490件と初めて10万件を超え、同様に、04年(6万6592件)の約1.57倍に増加しています。
では、なぜ、遺言書を作成する必要があるのでしょうか。
遺言書がない場合には、民法が規定する「法定相続分」(各相続人が取得すべき相続財産の総額に対する「割合」)に従って遺産を分けることになりますが、民法は、「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」、「配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする」、「配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする」などと規定しているだけです(民法900条)。
具体的に、誰がどの遺産、例えば自宅は誰が相続するのか、預金や株式といった金融資産の分配はどうするのかなど、個々具体的な遺産の帰属を決めるためには、相続人全員で遺産分割協議、つまり自主的な話し合いを行わなければなりません。
しかし、例えば、特定の相続人が、遺産のうち自宅不動産を欲しいと主張したり、複数ある不動産のうちのどこどこが欲しいと主張したりするなど、相続人間でもめてしまい、話し合いで自主的に解決できないことが頻繁に見受けられます。そして、話し合いで解決できない場合、家庭裁判所における調停や審判などで解決することになりますが、争いが深刻化して解決が困難な事例や、解決のために長期間かかる事例も見られます。また、解決できたとしても、それを契機に相続人間で絶縁状態になってしまうといったこともよくあります。
そこで、事前に、遺言書によって、配偶者には自宅と現金200万円、長男には現金500万円、長女には株式、次男には別荘などというように、具体的に個別財産の帰属を決めておけば、遺産は遺言書に従って分配されることになりますから、分配を巡る無用な争いを避けることができます。
また、相続分は民法で規定されていますが、ある特定の相続人には法定相続分よりも多くの遺産を与えたいと考える場合もあるでしょう。例えば、子供の相続分は等しいものとされていますが、家業を継いで、また長年同居して老後の世話をしてくれた長男には、数年に1回しか訪ねてこない次男よりも多くの遺産を与えたいなどと考えるのは、心情的にも、また家業を守っていくためにも理解できるところです。そこで、事前に遺言書において、長男には自宅及び家業の店舗と500万円、次男には400万円というように、長男には、次男より多くの遺産を分配すると決めておけば、原則として、その遺言書に従って遺産を分配することができることになります。
つまり、遺言書とは、自分が生涯をかけて築いてきた、あるいは、先祖から引き継いできた大切な財産、つまり遺産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者(被相続人)の意思表示です。遺言書の最も重要な機能は、遺産の処分に関して、遺言者の意思を反映させることにあると考えられます。
特に遺言書を作成しておいた方がよいと考えられる場合
上述のように、不要な争いを避けるためにも、一般的に遺言書を作成しておくことが良いと考えられます。もちろん、遺言書を残さない場合に、全て紛争につながるわけではありませんから、むしろ、相続人間の自由な協議に委ねたいと考えることも可能です。そういう意味では、遺言書作成が必須ということにはならないわけですが、次のような場合などは、遺言書を作成しておく必要性が非常に高いと考えられるので、そういった状況にある人は、真剣に遺言書の作成を検討することをお勧めします。
(1)夫婦間に子供がない場合
(2)法定相続人以外の人に遺産を与えたい場合
(3)先妻の子供と後妻がいる場合
(4)事業を特定の法定相続人に承継させたい場合
(5)相続人がいない場合
(1)夫婦間に子供がない場合
前述のように、遺言書がない場合には、法律で定められた遺産を相続できる人(法定相続人)が遺産を取得することになります。子供がいる夫婦の場合、法定相続人は、被相続人の配偶者と子供になります。つまり、配偶者と子供がいる場合、その他の親族は、遺産を相続できる立場にはありません。しかし、夫婦間に子供がなく、配偶者だけしかいないという場合、単純に、その配偶者だけが法定相続人になるというわけではないので注意が必要です。この場合、法定相続人は、配偶者と被相続人の直系尊属(両親)となって、仮に直系尊属がいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹とされているのです。
そして、民法は、前述のように、法定相続人それぞれにつき、法定相続分を規定しています。相続人が配偶者と子供の場合には、配偶者が2分の1、子供が2分の1に分けることになりますが、仮に、子供がいない場合で直系尊属がいる場合は、配偶者が3分の2で直系尊属が3分の1、子供も直系尊属もいない場合で兄弟姉妹がいる場合は、配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1とされています。つまり、子供がいない夫婦で、夫が遺言書を作成しないまま死亡してしまうと、奥さんばかりではなく、夫の両親や兄弟姉妹も法定相続人として一定の相続分を有することになるわけです。
このようなケースの場合、通常は、夫の両親や兄弟が残された奥さんに対し強く権利を主張することなどなく、相続放棄をするなりして、円満に解決されることがよく見受けられます。特に、兄弟姉妹の場合には、遺族に対して自分の相続分をよこせと権利を主張するのは、世間体からも、はばかられるということなのかと思われます。ただ、自分の兄弟の奥さんといっても、日頃から親戚としての親しい交流がなければ、血のつながりのない他人と何も変わりませんから、もらえるものなら全てもらっておこうという気持ちを持つ人が出てくることはよくある話です。つまり、子供のいない夫婦が何も対策を講じないでおくと、残された奥さんが、相続を巡って、夫の親族(特に兄弟姉妹)ともめる可能性があるということです。そこで、そういう場合には、全財産を妻に与えるといった遺言をしておくことが必要となるわけです。特に、兄弟姉妹の場合には、後述する「遺留分」というものがありませんので、遺言書さえ作成しておけば、確実に全財産を妻に与えることができます。
(2)法定相続人以外の人に遺産を与えたい場合(代表的ケースだけ)
(a)内縁の配偶者がいる場合
最近では、夫婦同姓制度に反対するなどの理由で、婚姻届を提出しない実質婚を選択する夫婦も多いようです。しかし、夫婦として長年連れ添っていても、婚姻届を提出していない場合、法律的には内縁の夫婦関係となって、夫が死亡した場合でも相続権はありません。そこで、パートナーに遺産を与えたい場合には、必ず、遺言書を作成しておかなければなりません。なお、昨年末に最高裁判所が出した、夫婦同姓を合憲とする判決に関心がある方は、本コーナー「夫婦同姓合憲、再婚禁止100日超は違憲 今後は?」(2015年12月24)をご参照下さい。
(b)子供の配偶者などに遺産を与えたい場合
例えば、子供である長男が死亡した後も、長男の妻が、長男の親の老後の世話をしているような場合も多いと思います。この場合、長男の妻は、夫である長男の親の法定相続人ではありませんから、遺言書がないと、長男の妻に遺産を与えることはできません。感謝の気持ちなどから遺産を与えたいという場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
(c)配偶者の連れ子と養子縁組していない場合
配偶者に連れ子がいる場合、配偶者と結婚しただけでは、その連れ子とは親子になるわけではなく、親子となるには、養子縁組をする必要があります。養子縁組をしていない場合、配偶者の連れ子は法定相続人にはなりませんので、その子に対して遺産を与えたい場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
(d)親族以外の第三者に遺産を与えたい場合
例えば、介護でお世話になった介護福祉士にお礼のために遺産の一部を与えたいと思った場合や、慈善団体に遺産を寄付したいと思った場合などのように、法定相続人以外の第三者には、遺言書がなければ、遺産を与えることはできません。
(3)先妻の子供と後妻がいる場合
離婚した場合、離婚した元配偶者は法定相続人ではなくなりますが、元配偶者との間の子供は法定相続人であることに変わりありません。例えば、再婚して後妻がいる場合、先妻の子供と後妻との間では遺産争いが起きる可能性が高く(特に後妻と不倫の末に再婚したような場合など)、遺産分割協議でもめることを防ぐためには、遺言書を作成しておく必要性があります。
(4)事業を特定の法定相続人に承継させたい場合
例えば、株式会社のオーナー社長が長男を後継者としたい場合でも、遺言書がないと、所有する株式、営業所や工場等の事業用資産など(オーナーの所有物である場合)が複数の相続人に分割されてしまい、会社の運営に支障を来したり、最悪の場合には廃業に追い込まれたりする事態も考えられます。このような事態を避けるためには、特定の者に事業を承継させるための策を講じた内容の遺言書を作成しておくことが必要になります。
(5)相続人がいない場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属することになってしまいます。財産が国に渡ってしまうくらいなら、お世話になった方にお礼をしたいとか、慈善団体等に寄付して遺産を有意義に使ってもらいたいといった意思がある場合、その旨の遺言書を作成しておくことが必要になります。
遺言書の種類・要件について
では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか。
遺言書は、遺言した人の意思を確実に実現させる必要があるため、民法において(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つの方式が定められており、その要件が厳格に規定されています。この方式に従わなかったり、要件を欠いたりしたものは全て無効とされてしまいます。
以下、(1)と(2)について説明したいと思います。なお(3)の秘密証書遺言ですが、これはあまり利用されていないので、ここでは割愛したいと思います
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」とされています。全てを自書しなければならず、パソコンなどで作成したものや、他人に代筆してもらったものなどは無効ですが、印は三文判でも構いません。自筆証書遺言は、要件を満たせば、費用もかからずに、一人で簡単に作成できて便利です。
しかし、自筆証書遺言は、冒頭で説明したように、修正にも厳格な方式が規定されており、場合によっては方式不備によって無効にされてしまう危険があります。また、自筆証書遺言の場合、遺言書を保管している者または遺言書を発見した者が、家庭裁判所で「検認」という面倒な手続きをしなければなりませんし、発見した者が、自筆遺言証書を読んで自分に不利な内容であった場合に破棄したり、隠したり
冒頭の最高裁判所の事件では争われませんでしたが、遺言書に斜線を引くなどは誰でも簡単にできますので、同様の事案が発生した場合には、誰が斜線を引いたかということが争われる可能性もあります。
遺言書を作成する目的は、相続人間での不要な争いを避けるためですが、冒頭で述べた最高裁判所の事案のように、自筆証書遺言の場合には、法律に則してきちんと作成しないと、その存在自体が、かえって不要な紛争を招来してしまう可能性も否定できないので注意が必要です。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、以下の方式に従って作成されます。
(1)証人2人以上が立ち会い
(2)遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授すること
(3)公証人が、遺言書の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
(5)公証人は、その証書は(1)から(4)の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
公証人とは、元裁判官や元検察官など法律の専門家ですので、作成しようという内容が複雑であっても、法律的に正確に作成することができますし、自筆証書遺言と異なって、方式の不備で遺言が無効になる恐れはありません。また、公正証書遺言の場合、自筆証書遺言と違って、家庭裁判所の「検認」の手続きが不要であり、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されることから、遺言書が第三者によって破棄されたり、隠されたり、改竄されたりするおそれもありません。さらに、自書する体力がない人でも作成できますし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその理由を付記して、署名に代えることができるとされていますので、署名することができなくなってしまった人でも作成できます。つまり、遺言者が、公証役場にすら行くことができない状況の場合でも、公証人が自ら病院などの施設に出向いていって作成することができるわけです。このような形での遺言書の作成は特段珍しいものではなく、私も何度もそのような形で、公正証書遺言を作成する場に立ち会ったことがあります。
このように公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも安全で確実な方式となっています。デメリットとして、公正証書遺言の作成には、公証人の手数料がかかることが挙げられます。手数料は、遺言の対象となる遺産の評価額などにより定まりますので、一概には言えませんが、不要な争いを避けるための費用だと考えれば、それ程高額なものではないと考えられます。ちなみに、例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合、4万3000円となります。
遺留分とは
ここで、遺言書を作成する際に知っておく必要がある「遺留分」について、一応簡単に説明しておきたいと思います。
遺留分とは、簡単に言えば、遺産の最低限度の取り分として遺産の一定割合の取得を法が保障したものであり、それに反する内容の遺言書が仮にあっても、法定相続人はその最低限の財産を取得できるようになっています。
前述のように、遺言書の最も重要な機能は、遺産の処分に関して、遺言者の意思を反映させることにあると考えられており、遺言者は、原則として、遺言によって、自己の財産を自由に処分することができます。つまり、遺言書作成によって、法定相続人の1人に遺産を全部与えることも、法定相続人ではない第三者に遺産の全部を与えることもできるわけです。ただ、相続という制度には、遺族の生活保障や、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算といった機能もあると考えられていることから、民法は、遺留分制度という形により、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を、一定の法定相続人に対し保障する制度を設けたわけです。
従って、遺言書を作成する際には、遺留分の存在を考慮に入れておかないと、せっかく遺言書を作成したのに、斜線を引いた遺言書と同様に、相続人間で、遺留分を巡る紛争を引き起こすことになってしまいます。そうならないようにするためには、遺留分を侵害しない程度の範囲で、遺産の分配に軽重をつけるような形にすることが望ましいことになります。
ちなみに、遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属とされており、兄弟姉妹には認められていません。つまり、相談者の場合には、夫の兄弟姉妹に関する遺留分侵害について検討する必要はないことになります。
お兄さんに対する対応として
まず、相談者としては、最高裁判所の判例に従って、斜線が引かれた遺言書は無効であるとして、法定相続分である遺産の3分の1を主張することが考えられます。また、従前の父親との関係性から、遺言書の内容は予想したものでそれなりに納得できるというなら、遺言書の無効までは争わないで、遺留分についてのみ主張することも考えられます。相談者の場合、相続人が子供3人ということですから、その遺留分は財産の6分の1(法定相続分の2分の1)となります。
なお、遺留分制度は、民法に規定された遺留分を侵害する行為を当然に無効とするわけではありません。つまり、遺留分を侵害する遺言がなされた場合、そのまま放置すれば、遺言書通りに遺産が処分されることとなります。相談者が、自分の遺留分を主張したいなら、お兄さんに対して、一定の権利行使(遺留分減殺請求)をしなければなりません(この点の詳細は割愛しますが、非常に専門的な話になりますので、専門家に相談するのがよろしいかと思います)。
以上、遺言書を巡る法律関係について説明してきましたが、実のお兄さんとの間で、裁判にまで発展した場合、修復できないほど決定的な亀裂ができる可能性があります。以前、このコーナーで御紹介したように、私も、仲の良かった兄弟が、家庭裁判所の廊下でつかみ合いの
お父さんがなぜこのような遺言書を作成したのかも含めて、お兄さんとよく話し合われて、裁判所が関与するまでもなく、お互いに納得できる解決を図る努力をすることをお勧めしたいと思います。