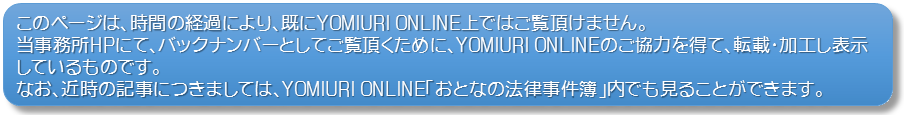終活ブーム、尊厳死や安楽死、日本ではどうなっているの?
h1>
相談者 S.Kさん
長年勤めた電機メーカーを5年前に退職、現在は妻と2人で悠々自適の生活をしています。最近、仲の良かった友人を相次いで亡くし、自分の死について深く考えるようになりました。「終活」を特集した雑誌をいくつか取り寄せ、自分なりの準備をしています。
自分の葬儀のスタイルを考えてみたり、お墓の手配をしたり、さらには弁護士に依頼して公正証書遺言を作成するといったことをやってみたのですが、終末期医療をどうするかで悩んでいます。自分が不治の病にかかり、医師から余命を宣告されたらどうするのか。家族に迷惑をかけたくないと思う一方で、自分がどんな最期を迎えるのか、なかなか考えがまとまりません。
以前、新聞で、脳腫瘍を患い余命わずかと宣告されたアメリカの29歳の女性が、オレゴン州で、医師による処方薬を服用して死亡した旨の記事を読んだことがあります。アメリカの一部の州では、このような死に方が認められているとのことでした。もうずっと昔のことですが、私の父は末期がんで苦しみながら亡くなっています。子どものころに読んだ手塚治虫の漫画『ブラックジャック』では、ドクター・キリコがそうした患者の安楽死を手助けしていましたが、今の日本では、安楽死は基本的に認められておらず、仮に医師が手助けをした場合には、医師が殺人や自殺
家族にあてたエンディングノートには、妻や子どもたちへの感謝の気持ちとともに、「無用な延命治療はしないでください」という私の希望を書きたいのですが、家族や治療にあたる医師に罪を負わせることはできません。延命治療のあり方についての関心は高まっているようですが、尊厳死、安楽死を巡る議論はどこまで進んでいるのでしょうか。法律的な面もあわせて教えてください。
(最近の事例をもとに創作したフィクションです)
(回答)
終活ブーム
最近、「終活」がブームになっているそうです。確かに、雑誌などでも、この言葉をよく見るようになった気がします。ネットで調べてみると、2012年のユーキャン新語・流行語大賞では、大賞こそ逃したものの、iPS細胞(人工多能性幹細胞)、LCC(格安航空会社)などという言葉と並んで、トップテンに選ばれています。
ウィキペディアでは、「終活」とは「人生の終わりのための活動」の略であり、人間が人生の最期を迎えるにあたって行うべきことを総括したことを意味する言葉と説明されています。具体的には、自分のお葬式の内容やお墓のことについてあらかじめ決めておいたり、財産や相続についての計画を立てて身辺整理をしておいたりする、といったような内容を指すようで、これらの活動を行うことにより、残された家族に迷惑をかけることもなくなり、安心して余生を過ごすことができるなどと言われています。こうしたブームの背後には、葬儀ビジネスによる商業的動機があるなどと批判的な意見もネットには出てきますが、仮にそうであるとしても、自分自身の人生の終わり方について、元気なうちから考えておくことは十分意義があると思います。
本コーナーの前回「斜線引いた遺言書が無効って本当? 有効な遺言書の作り方教えて」で説明した、遺言書の作成などが、終活のひとつであることは言うまでもありません。弁護士という職業柄、相続などでのもめ事をたくさん見てきているだけに、終活というものの大事さは身にしみて感じています。
さて、今回取りあげるのは、通常、終活という話題の時にはあまり取りあげられませんが、ある意味で、究極の終活とも言える、自分の死に方をどのように決めるかという問題です。
ブリタニー・メイナードさんの事例
14年1月、米国人女性ブリタニー・メイナードさんは、神経
ブリタニーさんは、医師から、治療による副作用など、病気の末期に体がどのような影響を受けるかを知らされ、衰弱が激しくなる前に自らの命を終えることに決めたということです。そして、ブリタニーさんは、居住していたカリフォルニア州サンフランシスコから、全米で初めて尊厳死を合法化する法律が施行されたオレゴン州に移住し、同年11月1日、医師から処方された鎮痛剤を、致死量を超えて服用して亡くなりました。死の直前には、家族や友人に対して、SNSで「さようなら、世界」などと書き込んだということです。
ブリタニーさんは、事前に、自ら「尊厳死」を選ぶ決意を表明して「11月1日に服薬で死ぬ」と予告する動画をユーチューブで公開していたため、世界中で賛否両論が巻き起こり話題となっていました。その動画の閲覧件数は1千万回を超えたということです。日本でも話題となり、同年11月4日付の読売新聞でも、「『尊厳死』宣言 薬飲み実行」という見出しで大きく取り扱われました。ブリタニーさんがこのような選択をするに至るまでの葛藤については、ネットでも様々な情報が提供されていますので、関心のある方はぜひ一読してもらいたいと思います。
「尊厳死」と「安楽死」の違い
ブリタニーさんのニュースを契機として、日本でも「尊厳死」について議論となりました。ただし、ここで注意すべきなのは、ブリタニーさんの事例は、いわば「医師による自殺幇助」を意味するものであり、厳密に言えば、日本では「尊厳死」ではなく、「安楽死」として議論されている事例に該当することです。
安楽死と尊厳死の違いについては、インターネット上でも様々な説明がなされています。ちなみに、その一例として、一般財団法人日本尊厳死協会のHPでは、次のように記載されています。
「尊厳死は、延命措置を断って自然死を迎えることです。これに対し、安楽死は、医師など第三者が薬物などを使って患者の死期を積極的に早めることです。どちらも『不治で末期』『本人の意思による』という共通項はありますが、『命を積極的に絶つ行為』の有無が決定的に違います」
いずれも本人の意思による死の迎え方ですが、安楽死は、薬物などによって人為的に死をもたらすものであるのに対して、尊厳死は「人間の尊厳を保って自然に死にたい」という患者の希望をかなえることを目的として、人工的な延命措置を行うのをやめ、その結果として自然な死を迎えるというものということだと思います。
ではなぜ、新聞各社が、ブリタニーさんの死を「尊厳死」として報じたのか、それは日米の法制度の違いに依拠します。アメリカでは、オレゴン州、ワシントン州、バーモント州、モンタナ州、ニューメキシコ州、カリフォルニア州の6州において、不治の病で終末期にある患者に、医師によって処方された死に至る薬を自分自身で服用して、自ら命を絶つことを認める法律、いわゆる「Death with Dignity Act」(DWDA)が制定されています(カリフォルニア州では、ブリタニーさんの事例のときには法律が制定されていなかったのですが、当該事例が契機となり、昨年9月に同法案が可決され、今年1月1日から施行されたばかりです)。
この「Death with Dignity」を直訳すれば、「尊厳死」ということになりますから、ブリタニーさんの死を報じる日本の新聞でも、そのように記載されていたわけです。しかし、それは、日本でいう「尊厳死」とは異なるものと考えられているということです。当時、日本尊厳死協会の担当者は、尊厳死と安楽死の区別が十分に理解されていないなど、終末医療について議論することがタブー視されている日本の現状について、読売新聞紙上でコメントしていました。
ちなみに、日本では「尊厳死」と言われている不治で末期に至った患者が、本人の意思に基づいて、死期を単に引き延ばすだけの延命措置を断り、尊厳を保って死に至ることなどは、アメリカでは「尊厳死」ではなく、「Natural Death」=「自然死」とされています。1976年カリフォルニア州で植物状態に陥った終末期において、生命維持装置を使用しない、または取り外すことを医師に要請する文書「リビング・ウィル(Living Will)」を、判断能力があるときに証人を立てて作成する権利を住民に保障する、世界初の法律が制定されましたが、この法律の名称は「Natural Death Act」=「自然死法」といいます。その後、他の州でも同様の法律が制定され、現在では、リビング・ウィルの要件・効果を定める法律がほとんどの州で制定されているとのことです。
以下、まず日本における「尊厳死」の現状について説明した上で、「安楽死」の問題(上記ブリタニーさんのようなケース)にも言及してみたいと思います。
東海大学安楽死事件
日本でいう「尊厳死」は、アメリカではほとんどの州で法的に認められているものの、日本では法制化されていません。しかし、現実の医療現場においては、延命措置を控えたり、中止したりすることは少なからず行われています。
ここで紹介する横浜地方裁判所・平成7年3月28日判決(東海大学安楽死事件)は、医師が患者に致死薬を投与するといった「安楽死」が、日本で初めて裁判で争われた事案として有名なものです。
本事案は、大学付属病院に勤務する医師が、治療不可能ながんに冒されて入院中の患者が余命数日という末期状態にあった時に、患者の長男ら家族から治療行為の中止を求められ、点滴などの全面的な治療を中止、さらに「楽にしてやってほしい」と頼まれて、塩化カリウムなどの薬物を注射し患者を死亡させたというものです。
裁判所は、治療行為の中止すなわち「尊厳死」の許容要件と、薬物の注射という「安楽死」の許容要件について判示した上で、医師の行為につき、「積極的安楽死として許容されるための重要な要件である肉体的苦痛及び患者の意思表示が欠けているので、それ自体積極的安楽死として許容されるものではなく、違法性が肯定でき、また、それに至るまでの過程において被告人が行った治療行為の中止……が、医療上の行為として法的許容要件を満たすものではなかったので、末期状態にあった本件患者に対して被告人によってとられた一連の行為を含めて全体的に評価しても……患者を死に致した行為は、その違法性が少ないとか、末期患者に対する措置として実質的に違法性がないとかいえず、有責性が微弱ともいえず、可罰的違法性ないし実質的違法性あるいは有責性が欠けるということはない」として、懲役2年執行猶予2年を言い渡しました。
日本における「尊厳死」の要件について
横浜地方裁判所は、まず、「治癒不可能な病気に冒された患者が回復の見込みがなく、治療を続けても迫っている死を避けられないとき、なお延命のための治療を続けなければならないのか、あるいは意味のない延命治療を中止することが許されるか、というのが治療行為の中止の問題であり、無駄な延命治療を打ち切って自然な死を迎えることを望むいわゆる尊厳死の問題でもある。こうした治療行為の中止は、意味のない治療を打ち切って人間としての尊厳性を保って自然な死を迎えたいという、患者の自己決定を尊重すべきであるとの患者の自己決定権の理論と、そうした意味のない治療行為までを行うことはもはや義務ではないとの医師の治療義務の限界を根拠に、一定の要件の下に許容されると考えられるのである」とした上で、「治療行為の中止」が許容される要件として、次の項目を挙げています。
(1)患者が治癒不可能な病気に冒され、回復の見込みがなく死が避けられない末期状態にあること
(2)治療行為の中止を求める患者の意思表示が存在し、それは治療行為の中止を行う時点で存在すること
(3)治療行為の中止の対象となる措置は、薬物投与、化学療法、人工透析、人工呼吸器、輸血、栄養・水分補給など、疾病を治療するための治療措置及び対症療法である治療措置、さらには生命維持のための治療措置など、すベてが対象となってよい。
そして、(1)の要件について、「治療の中止が患者の自己決定権に由来するとはいえ、その権利は、死そのものを選ぶ権利、死ぬ権利を認めたものではなく、死の迎え方ないし死に至る過程についての選択権を認めたにすぎないと考えられ、また、治癒不可能な病気とはいえ治療義務の限界を安易に容認することはできず、早すぎる治療の中止を認めることは、生命軽視の一般的風潮をもたらす危険があるので、生命を救助することが不可能で死を避けられず、単に延命を図るだけの措置しかできない状態になったときはじめて、そうした延命のための措置が、中止することが許されるか否かの検討の対象となると考えるべきであるからである。こうした死の回避不可能の状態に至ったか否かは、医学的にも判断に困難を伴うと考えられるので、複数の医師による反復した診断によるのが望ましいということがいえる。また、この死の回避不可能な状態というのも、中止の対象となる行為との関係である程度相対的にとらえられるのであって、当該対象となる行為の死期への影響の程度によって、中止が認められる状態は相対的に決してよく、もし死に対する影響の少ない行為ならば、その中止はより早い段階で認められ、死に結びつくような行為ならば、まさに死が迫った段階に至ってはじめて中止が許されるといえよう」としています。
さらに、(2)の要件については、「治療行為の中止のためには、それを求める患者の意思表示が存在することが必要であり、しかも、中止を決定し実施する段階でその存在が認められることが必要である」とした上で、「治療行為の中止を求める患者の意思表示は……十分な情報と正確な認識に基づいた明確なものとして、治療行為の中止が検討される段階で存在することか望ましく、医師側においてもそのような意思表示を求めて努力がなされるであろうが、しかし現実の医療の現場においては、死が避けられない末期患者にあっては意識さえも明瞭でなく、あるいは意識があったとしても、治療行為の中止の是非について意思表示を行うようなことは少なく、そのため、治療行為の中止が検討される段階で、中止について患者の明確な意思表示が存在しないことがはるかに多く、一方では、家族から治療の中止を求められたり、家族に意向を確認したりすることも少なくないと考えられるのである。こうした現実を踏まえ、今日国民の多くが意味のない治療行為の中止を容認していることや、将来国民の間にいわゆるリビング・ウィルによる意思表示が普及してゆくことを予想し、その有効性を確保することも必要であることなどを考慮すると、中止を検討する段階で患者の明確な意思表示が存在しないときには、患者の推定的意思によることを是認してよいと考えるのである」と判示して、患者の明確な意思表示が存在しない場合には、患者の推定的意思によることもできるとしています。
患者の明確な意思が存在しない場合
患者の明確な意思表示が存在しない場合における、患者の推定的意思の認定について、裁判所は、「まず、患者自身の事前の意思表示がある場合には、それが治療行為の中止が検討される段階での患者の推定的意思を認定するのに有力な証拠となる。事前の文書による意思表示(リビング・ウィル等)あるいは口頭による意思表示は、患者の推定的意思を認定する有力な証拠となる。こうした事前の意思表示も、中止が検討される段階で改めて本人によって再表明されれば、それはその段階での意思表示となることはいうまでもないが、一方、中止についての意思表示は、自己の病状、治療内容、予後等についての十分な情報と正確な認識に基づいてなされる必要があるので、事前の意思表示が、中止が検討されている時点とあまりにかけ離れた時点でなされたものであるとか、あるいはその内容が漠然としたものに過ぎないときには、後述する事前の意思表示がない場合と同様、家族の意思表示により補って患者の推定的意思の認定を行う必要があろう」とし、患者が事前に何らかの意思表示をしている場合には、患者自身の意思表示及び家族の意思表示によってこれを補うことによって、推定的意思の認定を行うとしています。
また、患者の事前の意思表示が何ら存在しない場合については、家族の意思表示から患者の意思を推定することが許されるとした上で、「家族の意思表示から患者の意思を推定するには、家族の意思表示がそうした推定をさせるに足りるだけのものでなければならないが、そのためには、意思表示をする家族が、患者の性格、価値観、人生観等について十分に知り、その意思を的確に推定しうる立場にあることが必要であり、さらに患者自身か意思表示をする場合と同様、患者の病状、治療内容、予後等について、十分な情報と正確な認識を持っていることが必要である。そして、患者の立場に立った上での
最高裁判所・平成21年12月7日判決(川崎協同病院事件)
最高裁判所・平成21年12月7日判決は、川崎協同病院において、気管支ぜん息の重症発作で心肺停止・意識不明状態となって入院した患者に対し、主治医が、家族からの要請に基づき、家族の目の前で気管内チューブを抜管しましたが、苦しそうな呼吸を繰り返したことから、准看護師に命じて、筋
本件は、前述した東海大学安楽死事件以降において、医師の刑事責任が問われ殺人罪で起訴された初めての事件であり、最高裁判所まで争われたことから、世間の注目を集めたものです。
同判決は、「被害者が気管支ぜん息の重積発作を起こして入院した後、本件抜管時までに、同人の余命等を判断するために必要とされる脳波等の検査は実施されておらず、発症からいまだ2週間の時点でもあり、その回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかったものと認められる。そして、被害者は、本件時、こん睡状態にあったものであるところ、本件気管内チューブの抜管は、被害者の回復をあきらめた家族からの要請に基づき行われたものであるが、その要請は上記の状況から認められるとおり被害者の病状等について適切な情報が伝えられた上でされたものではなく、上記抜管行為が被害者の推定的意思に基づくということもできない。以上によれば、上記抜管行為は、法律上許容される治療中止には当たらないというべきである」として、主治医に対して、殺人罪で懲役1年6月執行猶予3年の判決を下しました。
ちなみに、同判決の控訴審である東京高等裁判所・平成19年2月28日判決は、「尊厳死」の問題について、以下のように、解決するには法制化や国によるガイドラインの策定が必要との興味深い指摘を行っています。
「尊厳死の問題を抜本的に解決するには、尊厳死法の制定ないしこれに代わり得るガイドラインの策定が必要であろう。すなわち、尊厳死の問題は、より広い視野の下で、国民的な合意の形成を図るべき事柄であり、その成果を法律ないしこれに代わり得るガイドラインに結実させるべきなのである。そのためには、幅広い国民の意識や意見の聴取はもとより、終末期医療に関わる医師、看護師等の医療関係者の意見等の聴取もすこぶる重要である。世論形成に責任のあるマスコミの役割も大きい。これに対して、裁判所は、当該刑事事件の限られた記録の中でのみ検討を行わざるを得ない。むろん、尊厳死に関する一般的な文献や鑑定的な学術意見等を参照することはできるが、いくら頑張ってみてもそれ以上のことはできないのである。しかも、尊厳死を適法とする場合でも、単なる実体的な要件のみが必要なのではなく、必然的にその手続き的な要件も欠かせない。例えば、家族の同意が一要件になるとしても、同意書の要否やその様式等も当然に視野に入れなければならない。医師側の判断手続きやその主体をどうするかも重要であろう。このように手続き全般を構築しなければ、適切な尊厳死の実現は困難である。そういう意味でも法律ないしこれに代わり得るガイドラインの策定が肝要なのであり、この問題は、国を挙げて議論・検討すべきものであって、司法が抜本的な解決を図るような問題ではないのである」
厚生労働省によるガイドライン
厚生労働省は、2007年5月、「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定しています。
ガイドラインでは、終末期医療及びケアの在り方として、(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上で、終末期医療を進めることが最も重要な原則である(2)終末期医療における医療行為の開始・不開始、医療内容の変更、医療行為の中止等は、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである(3)医療・ケアチームにより可能な限り
また、終末期医療及びケアの方針の決定手続きとしては、患者の意思が確認できる場合には、(1)専門的な医学的検討を踏まえたうえでインフォームド・コンセントに基づく患者の意思決定を基本とし、多専門職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームとして行う(2)治療方針の決定に際し、患者と医療従事者とが十分な話し合いを行い、患者が意思決定を行い、その合意内容を文書にまとめておくものとする。上記の場合は、時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また患者の意思が変化するものであることに留意して、その都度説明し患者の意思の再確認を行うことが必要である(3)このプロセスにおいて、患者が拒まない限り、決定内容を家族にも知らせることが望ましい、としています。
他方、患者の意思が確認できない場合には、(1)家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする(2)家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする(3)家族がいない場合及び家族が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする、としています。
そして、終末期医療及びケアの方針の決定に際しては、医療・ケアチームの中で病態等により医療内容の決定が困難な場合や、患者と医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合、また、家族の中で意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いの中で、妥当で適切な医療内容についての合意が得られない場合には、複数の専門家からなる委員会を別途設置し、治療方針等についての検討及び助言を行うことが必要である、などとしています。
なお、同ガイドラインは、昨年3月に改訂され、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」と改称されています。最期まで尊厳を尊重した人間の生き方に着目した医療を目指すことが重要であるとの考え方によるものです。内容的には大きな変更はなされていません。厚生労働省では、分かりやすいリーフレットなども配布しており、PDFのダウンロードもできますので、関心のある方はご覧になって下さい。
「尊厳死」法制化の動き
このように厚生労働省からガイドラインは示されているものの、医療機関としては、場合によっては刑事責任を追及されかねないために、生命維持治療を開始した患者に対して中止することは容易にできない上、どのような条件を満たし、手続きを踏めば免責されるのかについて、法律で明記されていないことから、慎重にならざるを得ないといった現状にあります。
こうした現状を打開するために、超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」が、議員立法として「尊厳死法案」の国会への提出を検討していると昨年報道されました。提出が検討されていた法案には2案ありますが、いずれの法案も適切な医療上の措置を受けた場合であっても患者が回復する可能性がなく、死期が間近であると判定された状態を「終末期」とした上で、15歳以上の患者が延命措置を望まないという意思を書面その他の厚生労働省令で定める方法で表示しており、かつ2人以上の医師が終末期と判断した場合には、いわゆる「尊厳死」を認め、医師は、民事上、刑事上、行政上の責任を問われない、また、意思表示はいつでも撤回できるとするものです。2案で異なる点は、第1案が「延命措置の不開始」を認めるものであるのに対し、第2案は、「延命措置の中止等」、つまり、「延命措置の不開始」に加えて、実施中の延命措置を中止することも認めるものとなっています。
一般財団法人日本尊厳死協会は、「延命治療の中止を求めても、医療機関に受け入れてもらえないケースがあります。医師は人の命を助けることが使命ですから、人工呼吸器を装着しないことや、それをはずしてしまうことに抵抗があるのです。さらには、医師自身が罪に問われることを懸念するためでもあります。自分の最期は、自分で決めるというリビング・ウィルの精神が生かされるためには、これらの意思を法律でみとめてもらわねばなりません。結果として、医師が罪に問われることもなくなります。国会では、超党派の議員連盟ができて法案も作成されていますが、実質的な審議にはいたっていません。私たちは実質的な審議となるよう、提言・要望活動を行っています」と法制化を支持しています。
しかし、「尊厳死」の法制化には反対意見も多いようです。難病患者や障害者団体などからは、延命措置の中止は命の軽視につながる、医師が
このように「尊厳死」法制化については賛否両論があり、今のところ、法案は、国会への提出がなされていません。
日本における「安楽死」
上記のように法制化まで議論されている「尊厳死」とは異なり、「安楽死」の法制化を求める動きはいまだにみられないようです。
日本における「尊厳死」の法制化を推進している日本尊厳死協会は、HP上で「安楽死を支持していません」と明確に意見表明していますし、日本臨床倫理学会も、HP上で、「ブリタニー・メイナードのケース」と題するリポートを掲示し、「日本では、医師による致死薬の処方を受け、自分の死亡する日時を自己決定し、自分で服薬するということが許容される社会的合意はありません。また、このような行為は、患者の命を救うことが使命である医師の価値観を大きく揺るがせることになりかねないだけに、さらに議論が必要です」としています。
また、アメリカでも、ブリタニーさんが自ら命を絶つことを認める根拠となった法律である「Death with Dignity Act」については反対意見も根強いようです。今年1月1日から同法が施行されたカリフォルニア州でも、法案は可決されたものの、州下院では賛成43、反対34で、また州上院でも賛成23、反対14と、多くの反対票が投じられています。
ちなみに、前述の横浜地方裁判所・平成7年3月28日判決は、「末期医療においては患者の苦痛の除去・緩和ということが大きな問題となり……治療行為の中止がなされつつも、あるいはそれがなされても患者に苦痛があるとき、その苦痛の除去・緩和のための措置が最も求められるところであるが、時としてそうした措置が患者の死に影響を及ぼすことがあり、あるいは苦痛から逃れるため死に致すことを望まれることがあるかもしれない。そこで、いわゆる安楽死の問題が生じるのであり、本件でも被告人は、治療行為を中止した後、家族からの『苦しそうなので、何とかしてほしい』『早く楽にさせてほしい』との言葉を入れて……患者を死に致したのであって、外形的には安楽死に当たるとも見えるので、安楽死が許容されるための一般的要件について考察してみる」とした上で、安楽死が許容される要件として、次の項目を挙げています。
(1)患者が耐えがたい肉体的苦痛に苦しんでいること
(2)患者は死が避けられず、その末期が迫っていること
(3)患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くし他に代替手段がないこと
(4)生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
尊厳死、安楽死を巡る議論の今後
以上、「尊厳死」と「安楽死」の現状について、極力中立的な立場で議論してきましたが、いずれも、誰にでも必ず訪れる「死」をどのように迎えるかという重要な問題であり、多くの国民の意見を反映すべく、慎重に議論していくべきであることは言うまでもありません。
最後に、近時、安楽死の問題が話題になった事件を紹介したいと思います。
昨年7月8日、痛みに耐えられない妻(当時83歳)から殺してほしいと懇願され、ネクタイで首を絞め,その後死亡させたとして,嘱託殺人罪に問われた夫(当時92歳)について、千葉地方裁判所は、被告人(夫)は92歳の高齢で軽度の認知症を抱えながらも、自宅において被害者とほぼ2人きりの閉ざされた環境で眠る間もなく献身的に介護を続ける中で、次第に疲弊し追い詰められ,被害者を早期に苦しみから解放することを最優先に及んだ犯行だとして、懲役3年、執行猶予5年の温情判決を言い渡しました。
裁判所が認定した「犯行に至る経緯」の中には、安楽死に言及した、次のような一節があります。
「被害者は、足腰の痛みを和らげるために病院を何度も受診し、処方された鎮痛薬を服用するなどしていたものの、効果は乏しく、絶えず痛みに
判決言い渡し後、裁判官は「今度会った時に妻が悲しまないよう、穏やかな日々をお過ごしになることを願っています」と話し掛けたそうです。
社会の高齢化が進んでいく中、「尊厳死」の問題はもちろんですが、「安楽死」の問題も、タブー視するのではなく、国民的な議論が進んでいくべきテーマであると思います。